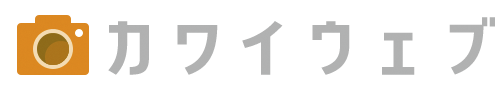言葉とイメージの相互関係により生み出された詩歌や物語は、現実とは異なる虚構の世界を表現している。
しかし、作家と作品を包含した存在として眺めた時、文学によって紡がれる人間の内面的なものを感じることができるのだ。
南米アルゼンチン出身の作家ホルヘ・ルイス・ボルヘス(1899~1986)は、その時々の事柄の状況に忠実であるよりも、夢とは何かを伝えようと努めた。
夢に忠実であろうと努力しながら、自己の生きている現実世界の相互関係のなか宇宙の図書館の住人となって多くの物語の魂を蘇らせたのである。
ボルヘスは、自身が物語のなかに登場する、幻惑的な独特の幻想の世界を創りあげたのだ。
宇宙図書館の住人、ホルヘ・ルイス・ボルヘス
ボルヘスは、詩人であり、ひとつの宇宙を形づくる幻惑的で幻想的な短編小説などの作品でも知られた、南米アルゼンチン出身の作家である。
1967年秋、アメリカ合衆国ハーヴァード大学で行われた講演の記録であるテキスト『詩という仕事について』(J・L・ボルヘス『詩という仕事について』鼓直訳、岩波文庫、2011年)のなかで彼は自身の作品を含めた詩についての感覚として、さまざまな詩を引用しながら詩や文学について、または自身の作品を生み出す過程について語っている。
書物を腑分けし書き楽しむなかで、楽しむことが何よりも大切で文学は再発見してゆくものであり「詩を汲む」ことを最終的な結論だと語る。
自分が提供できるものは劫を経た難題の提供に他ならないとしながら、
哲学の歴史が困惑の歴史であることとなぞらえて、詩を探求することと生を探求することは困惑を分かち合う事、ボルヘス自身が詩や文学で表現することと生きることが通底する意味であることを語っている。
ラルフ・ウォルド―・エマソン(1803~82)の言葉を引用して
「図書館は、死者らで満ち溢れた魔の洞窟である、と。しかも、これらの死者は甦ることが可能なのです。我々がページを開くと、生命を回復することが可能なのです。」 [註1]
またバークリー主教(1685~1753)から
「林檎の味覚は林檎そのものには無く―林檎自体は味を持たない―林檎を食する者の口のなかにも無い、両者の接触が必要である、」 [註1] と引用している。
書物は物理的なモノであり生命なき記号の集合体である。
しかし、まともな読者が現れると陰に潜んでいた言葉は息を吹き返して我々の世界へ甦る、書物によって触発された新しい詩を生むのである。
多くの書物を蘇らせボルヘスの作品内に内在する物語はボルヘスにより蘇った魂と、また新しい詩が生み出されているのだ。
また隠喩にとって重要な点をあげ、受容する側に隠喩として感じとられる事や、形式として目と星、目から成る怪物など、同じ形式に還元可能なイメージをあげている。
さらに「時の流れ」や「河のように流れる時」などの形式から、隠喩の夢としての生の形式、生は一場の夢に過ぎないという感覚から生じる形式として、
荘子の『胡蝶の夢』を例にあげ、この隠喩はもっとも精妙であり、蝶の精細ではかない印象を選んでいる荘子は、言いたい事と合致した言葉を選んでいると語る。
他にもさまざまな隠喩の例をあげ、数百、数千の隠喩の形式は少数の隠喩の形式に帰着させることができると伝える。
また明確な形式に帰着されない隠喩が存在するとして、隠喩とは実に洋々たるものがあるとボルヘスは考えるのだ。
新しい隠喩の創造は我々に許され、それを期待してはいけない理由は存在しないと引用から新たに生まれた隠喩による新しい表現の可能性を見出すことの重要性を伝えている。
人類にとって古代からの三つの物語である、トロイの物語、ユリシーズの物語、イエスの物語を例にあげ、
それらは音楽や絵画になり、人々は何度となくそれらの物語を語り、尽き果てることなく現在もそこに存在する事から、人間は多くの物語を必要としない事実を知ることができると考える。
叙事詩は人間が必要としている一つであると信じ小説よりも短編や物語を称揚し、物語を聞く喜びに加えて詩という高尚な喜びが得られれば素晴らしい何かが生まれると語る。
未来には叙事詩が我々のもとに帰ってくることもあり、詩人が創造者になると考えている。
また言語は長い時間をかけながら農民によって、漁民によって、猟師によって、牧夫によって生み出されてきた、図書館などで生じたものではなく、野原、海、河、夜、明け方から生まれたものであり、庶民が生きることから言葉が生み出された事を示している。
ボルヘスは自身の作品に対して読者もその作品に関与し、一種の共同作業であり、またボルヘス自身も読者である事を語り、文学が作者と読者の相互関係のなか生み出されていることを伝える。
自己の詩の作品を理性としての意味よりも、音楽のように感じてほしいと語ることから、庶民的な人類の世界で生きた文学であろうとする事が示唆されるのであるのだ。
ボルヘスは自身の想像力に忠実であろうとする、詩や作品を書く時、事実としての真実ではなく、それよりも深い何物かにとって真実であることを考える。
ある物語を書く時も歴史ではなく、ある夢とかある観念を信じているのだ。
芸術の歴史を意識するより、日時を考慮しなくても芸術の完成度を認識できるという考え方を意識する態度を持ち。
インド人が歴史感覚からでなく、あらゆる思想家を同時代の人間として扱い、古代哲学の用語を今日の哲学の新しい表現に翻訳する考えを優れていると考える。
人が哲学と詩を信じる事、そして昔美しかったものは現在も美しくあり続けること、この無時間的な普遍性を称揚し夢とは何かを伝えようと努めるのだ。
これらの要素を包含させ、ボルヘスは自己を通して多くの書物の魂を甦らせる。
さらにボルヘスという人間の生きた夢の内面描写が融合されながら、迷路に入るような、ひとつの宇宙を形づくる作品が生み出されるのである。
言葉とイメージの相互関係により生み出された詩歌や物語は、現実とは異なる虚構の世界を描いている。
しかし、作家と作品を包含した存在として眺めた時、文学によって紡がれる人間の内面的なものを感じることができるのだ。
作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスは、その時々の事柄の状況に忠実であるよりも、夢とは何かを伝えようと努め表現するのである。
その夢に忠実であろうとする表現は、自己の生きている現実世界との相互関係とつながりながら宇宙の図書館の住人となって多くの物語の魂を蘇らせるのだ。
そして、自身が物語のなかに登場する幻惑的な独特の幻想の世界を創りあげたのである。
参考文献、ホルヘ・ルイス・ ボルヘス『詩という仕事について』、岩波文庫、2011年 [註1]9ページ、 ホルヘ・ルイス・ボルヘス/篠田一士訳『伝奇衆/エル・アレフ』、グーテンベルク21、2017年、 ホルヘ・ルイス・ボルヘス/柳瀬尚紀訳『ボルヘス怪奇譚集』、河出書房新社、2018年、 ホルヘ・ルイス・ボルヘス/野谷文昭訳『七つの夜』、岩波書店、2018年
 ホルヘ・ルイス・ボルヘス『詩という仕事について』普遍的な生の表現。(文芸)
ホルヘ・ルイス・ボルヘス『詩という仕事について』普遍的な生の表現。(文芸) 前衛文学の作家、ホルヘ・ルイス・ボルヘス(文芸)
前衛文学の作家、ホルヘ・ルイス・ボルヘス(文芸)