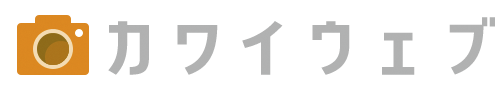この記事は、2020年5月25日に推敲、更新しています。
言葉を道具として使用した人間は自身の物語を創造し、精神という脳内と外側に生きる現実のふたつの世界を生きている。
その相互関係のなかで芸術は古代から多くの物語を紡いでいるのだ。
インターネットを思考の土台としている現在では、多くの情報の中で時間軸を超えた表現を可能にさせている。
デジタルメディアとなって画像の加工や修正などの「変成の遊戯」を手に入れた写真は、一方で人間が無意識に見ている風景の存在を機械的に定着した超現実として表現し、他方で意識的な視覚として空想・創造と理想を描いている。
それは脳内と現実を生きる人間のパラレルな世界を視覚表現することに繋がるのだ。
ゆえに、写真は芸術という分野に新しい二次元世界を生み出すと示唆されるのである。
デジタルメディア時代の写真の可能性
1839年、ルイ・ジャック・マンデ・ダゲール(1789~1851)によって正式に公開された写真技術は、
19世紀終わりごろから、先行する二次元表現メディアである絵画芸術を写真で再現しようとした動きが見られた。
20世紀にはいると「絵画主義(ピクトリアリズム)写真」写真と絵画の境界を侵犯した写真の可能性をひろげるものが、各国のアマチュアたちの間で流行した。
その後フォーマリズム、モダニズムといわれる写真の自立性を重んじる運動があり、1920年代ドイツでは、写真の客観性を重視した「新即物主義」という運動が展開され、1930年代アメリカでは、徹底的に細部の鮮鋭さを追求したストレート写真、印画紙に必要以上の技工を凝らさない、モダニズム写真運動が、グラフ雑誌『ライフ』の創刊と相まって道を開くのだ。
1930年にはレンズの発達、感光材料の改良、ライカなどのフィルム式小型カメラの普及、
1935年には、コダクローム法の発表でカラー写真を撮影することが可能になり、1970年代には芸術写真にもカラー写真が使用され始めた。
1960年代にはポストモダンの芸術家たちが、美術と写真という二項対立をなしくずしにする。
1970年代には「虚構」としてのイメージの積層させる写真表現が、杉本博司(1948~)によって展開される。森村泰昌(1951~)は85年以降に演劇的な装置あるいは合成技術を用い、「構成された写真」人工的な演出写真を見せる。
1980年代中盤に開発されたデジタル写真は、急激な技術改良によって、2005年には銀塩とのシェアを逆転するのだ。
90年代に入り、コンピューターグラフィックスを駆使した、写真表現の拡張が行われ、写真と美術の境界は行き来することになるのである。
写真というメディアは、デジタルメディア時代の現在ではコンピューターグラフィックスとの融合を可能にさせた。
またハードウェア側の技術革新や写真のデジタル画像加工技術の深化によって、より美術世界に接近する側面を持つことになっている。
今後、写真というメディアは、一方で人間が無意識に見ている風景の存在を機械的に表現するシュルレアリスムを踏襲し、他方で意識的な視覚として空想・創造と理想を表現する。
それは脳内と現実を生きる人間のパラレルな世界を視覚表現することと通底し、芸術という分野に新しい二次元世界を生み出すと考えられるのであり、芸術世界へ大きな意義をもつと示唆されるのだ。
参考文献 飯沢耕太郎『写真的思考』株式会社河出書房新社・2009年
『写真の変容と拡張』京都造形芸術大学・1999年 、編者・林洋子『芸術教養シリーズ8 近現代の芸術史 造形篇2 アジア・アフリカと新しい潮流』京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局・芸術学舎、2013年、